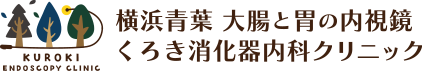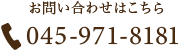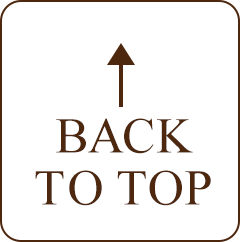排泄の仕組み
 消化管は、私たちが摂取した飲食物を分解・消化して、栄養や水分を吸収します。体に不要となった老廃物を便として排泄します。口から入った食べ物が便として排泄されるまでには、通常約24~48時間かかります。この過程では、脊髄と脳の緊密に連携して働きます。
消化管は、私たちが摂取した飲食物を分解・消化して、栄養や水分を吸収します。体に不要となった老廃物を便として排泄します。口から入った食べ物が便として排泄されるまでには、通常約24~48時間かかります。この過程では、脊髄と脳の緊密に連携して働きます。
食べ物が胃に入ると、まず脊髄に信号が送られます。その信号を受け取った脳は、再び脊髄を介して腸に「便を出す」という指令を送ります。この一連の流れを「胃・結腸反射」と呼んでいます。
胃で消化された食べ物は大腸へと送られ、そこで便が作られます。作られた便は脳からの信号によって直腸へと移動し、便意を感じ、最終的に排泄されます。
大腸は不要物の処理や便の一時的な貯蔵を担う重要な器官ですが、そのため、負担がかかりやすく病気になりやすい器官です。便の成分は水分が70~80%、固形分は食事由来、腸管壁の代謝物、腸内細菌がそれぞれ1/3ずつを占めています。
どこからが便秘?下痢?
便秘や下痢は、誰もが日常生活で経験する身体の悩みの一つです。
便秘には、さまざまな原因があります。例えば、運動不足による腹筋の衰え、水分や食物繊維の摂取不足、極端なダイエット、ストレスによる腸の動きの低下などが挙げられます。また、消化器系の病気が原因となっているケースもあります。
下痢についても、複数の原因が考えられます。暴飲暴食やストレス、食中毒の原因となる細菌やウイルスの感染、腸の水分吸収能力の低下などが主な原因です。便秘と同様に、消化器系の病気が引き起こしている可能性もあります。
なお、便の状態を客観的に判断する基準として、医療現場では「ブリストル便形状スケール」が広く採用されています。
ブリストル便形状スケール
| スケール | 便の形状 | 特徴 | 消化管の通過時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | コロコロ便 | ウサギの糞に似た、硬く丸い便 | 極めて遅い (約100時間) |
| 2 | 硬い便 | ソーセージ状だが硬い便 | |
|
3 |
やや硬い便 | 表面がひび割れたソーセージ状の便 | |
| 4 |
普通便 |
滑らかで柔らかいソーセージ状またはコイル状の蛇のような便 | |
| 5 | やや柔らかい便 | しわのはっきりした半固形状の柔らかい便 | |
| 6 |
泥状便 |
形が崩れた小さな便で、柔らかく、形が整っていない泥状の便 | |
| 7 | 水様便 | 水っぽく、固形物を含まない便 | 極めて早い(約10時間) |
1と2は便秘、3~5は正常な便、6と7は下痢を意味します。排便後、すっきりお腹が空っぽになった感じがしない場合、便秘と定義されます。
また、下痢と便秘は両極端な症状のように思えますが、病気によっては交互に起こることもあります。
下痢が続く、水下痢などで
お悩みではありませんか?
 お腹の不調や下痢、便秘の原因を病気の症状だと考える方は、あまり多くないものです。多くの場合、「冷たいものを食べ過ぎたから」「お酒を飲み過ぎたから」「疲れているから」などと、一時的な原因だと考えがちです。
お腹の不調や下痢、便秘の原因を病気の症状だと考える方は、あまり多くないものです。多くの場合、「冷たいものを食べ過ぎたから」「お酒を飲み過ぎたから」「疲れているから」などと、一時的な原因だと考えがちです。
確かに、冷たい食べ物や飲み物の取り過ぎ、脱水症状、ストレスなどが原因で下痢になることはあります。しかし、これらの症状が腸の病気によるものである可能性も否定できません。そのため、安易に症状を放置することは危険です。特に、下痢が長引く場合や、便に血が混じっている場合、便秘と下痢を繰り返す場合などは、早めに医療機関を受診することをお勧めします。
「下痢しやすい体質だから」と思い込んで、適切な治療を受けない方もいらっしゃいます。しかし、継続的な下痢は、何らかの体調不良のサインかもしれません。
以下のような症状がある場合は、特に注意が必要です。
-
これまでに経験したことがないような激しい下痢が続いている
-
便に血が混じっている
- 下痢と共に吐き気や嘔吐がある
-
排便後もお腹の痛みが続く
-
下痢の症状が徐々に悪化している
-
喉の渇きが異常に強い、または尿量が減少するなどの脱水症状がある
-
同じ食事をした人にも同様の下痢症状が見られる
-
下痢に発熱を伴う
これらの症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、適切な診察を受けることをお勧めします。
下痢の原因
急性の場合は短期間で症状が落ち着きますが、慢性の場合は1ヵ月以上にわたって下痢が続くことがあり、それぞれ原因が異なります。
急性下痢
主な原因は、細菌やウイルスに感染することによって起こる胃腸炎です。
慢性下痢
原因として多いのは過敏性腸症候群、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)などです。
その他、抗生物質など薬の影響、消化不良、ストレスなどが原因として考えられます。しかし、「長引く下痢」は大腸がんの症状としても考えられるため、自然に治るだろうと我慢せずに、早めに当クリニックへご相談ください。
下痢の場合に考えられる病気
感染性胃腸炎
感染性胃腸炎は、ウイルスや細菌などの病原体が消化管に感染することで引き起こされる病気です。主な症状として、激しい下痢や嘔吐、腹痛、発熱などが見られます。その他にも、頭痛や食欲不振を伴うことがあります。
感染経路は主に3つあります。汚染された食べ物や飲み物を摂取することによる感染、感染している方との直接的な接触、そしてドアノブなどウイルスが付着した物との接触です。予防するためには、食事前やトイレの後のこまめな手洗い、食品の十分な加熱、調理器具の清潔保持が重要です。また、体調不良の方との接触は避けることをお勧めします。
感染性胃腸炎の多くは、適切な水分補給と休養により自然に治癒します。しかし、脱水症状を防ぐため、水分とミネラルの十分な補給が大切です。症状が重い場合は、点滴などの治療が必要となることもあります。
以下のような症状がある場合は、早めに医療機関を受診してください。
激しい嘔吐が続く、水分が全く取れない、血便がある、高熱が続く、症状が改善しないなどの場合です。特に小さなお子様やご高齢の方は、症状が急激に悪化する可能性があるため、十分な注意が必要です。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)
潰瘍性大腸炎とクローン病は、原因不明の炎症性腸疾患(IBD:Inflammatory Bowel Disease)と呼ばれる慢性の腸炎です。両疾患とも、主に若い世代に発症することが特徴です。両方の病気に共通する主な症状として、下痢や腹痛、発熱などが見られます。特に潰瘍性大腸炎では、血便を伴うことが多いのが特徴です。
これらの病気は、現在の医学では完治は難しいものの、適切な治療により症状をコントロールすることが可能です。治療は主に薬物療法が中心となりますが、症状が重い場合には手術が必要となることもあります。
これらの病気は、疑って検査をしなければ正確な診断をすることが難しく、診断が遅れることで病状が進行してしまう可能性があります。そのため、血便が続く場合や、原因がはっきりしない下痢が長引く場合には、できるだけ早く専門医に相談することをお勧めします。
虚血性腸炎
虚血性腸炎は中高年の方に多く見られる病気で、腸の血流が悪くなることで起こります。
症状としては下痢や血便、腹痛(多くは左下腹部痛)などがありますが、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。
過敏性腸症候群(IBS)
便秘や下痢に伴う腹痛などの症状が起こり、排便すると楽になるという状態が続いているにも関わらず、検査をしても大腸に炎症や潰瘍などの器質的病変が見つからない場合は、過敏性腸症候群の可能性があります。過剰なストレスがIBSの原因になるとも言われており、症状としては、下痢と便秘を繰り返す傾向があります。
大腸がん
早期の大腸がんには自覚症状がほとんどありませんが、進行するにつれてさまざまな症状が現れることがあります。がんによって大腸の内腔が狭くなると、下痢と便秘が繰り返されるようになります。
慢性膵炎
慢性膵炎が進行すると、痛み以外に下痢や体重減少が起こることがあります。
また、すい臓の働きが低下することで消化酵素の分泌量が減り、脂肪の消化が難しくなるため、脂肪便と呼ばれる白く水様の便が排泄されることがあります。
下痢の場合の検査・診断
 多くの方が、下痢の原因を体質やストレスと自己判断し、医療機関への受診を控えています。しかし、下痢は潜在的な病気のサインである可能性があります。
多くの方が、下痢の原因を体質やストレスと自己判断し、医療機関への受診を控えています。しかし、下痢は潜在的な病気のサインである可能性があります。
血便、持続する下痢、便秘は体に異常があることを示しています。単に様子を見るのではなく、症状が継続する場合は、大腸カメラ検査を受けて大腸の健康状態を確認することが重要です。これにより、早期に病気を発見し、適切な治療につながる可能性があります。
下痢を早く治すには?
当クリニックで行う治療方法
急性の下痢の主な原因は、ウイルスや細菌による胃腸炎です。症状に応じて、整腸剤や抗生物質を使い分けて治療を行います。慢性の下痢の場合は、大腸カメラ検査などで原因を特定し、それに基づいた適切な治療を実施します。原因が不明な場合は、過敏性腸症候群の可能性を考慮し、ストレス管理や生活習慣の改善を通じて症状の緩和を目指します。
このような便秘症状で
お悩みではありませんか?
便秘の正しい理解と受診のタイミング
多くの人が、毎日排便がなければ便秘だと誤解していますが、排便の回数は個人によって異なります。2〜3日に1回の排便でも、不快な症状がなく便が残っていない場合は、正常な排便と言えます。
一方、毎日排便があっても、お腹がはって痛い、すっきりしない、便が出にくいなどのような症状がある場合は便秘と判断できます。
明確な便秘の定義はありませんが、排便に関する不快感や満足できない症状がある場合は、医療機関に相談することをお勧めします。
特に、次の症状がある場合は早めの受診をお勧めします。
-
便秘薬に頼っている
-
便が硬く、排便が困難で痛みがある
-
排便後もすっきりせず、腸に便が残っている感じがする
-
排便に時間がかかり、便の量が少ない
便秘で危険な症状
以下の症状は注意が必要です。
-
突然の便秘
-
便の形状変化(細くなる)
-
お腹のしこり
-
便に血や粘液が混ざる
-
改善しない深刻な便秘
-
激しい腹痛
- 嘔吐
- 発熱
また、便秘と下痢が交互に繰り返し発生する症状も警戒が必要です。
これらの症状は重大な病気のサインである可能性があります。身体に異変を感じたら、早めに医療機関に相談してください。
便秘の原因
便秘は大きく「機能性便秘」と「器質性便秘」に分けられます。ここではそれぞれの原因についてご紹介します。
機能性便秘
機能性便秘は、以下の3つのタイプに分類されます。
直腸性便秘
本来、便が直腸まで送られると便意を感じるのが一般的ですが、便意を我慢し続けたり、痔や加齢により直腸に便が残ったりすると、便意を感じなくなり便秘が発生します。
痙攣性便秘
生活リズムの乱れや過剰なストレスにより自律神経のバランスが崩れ、以下の症状が現れます。日々の生活リズムの乱れや過剰なストレスは、自律神経のバランスを崩す原因となります。その結果、腸管が硬化し、便が少量しか出ない、あるいは小さく硬い便がコロコロ出るといった状態になります。また、腹痛やお腹が張った感じ、便が出切っていない感じなどの症状が現れることもあります。
弛緩性便秘
腸の蠕動運動が弱まることで起こるのが弛緩性便秘です。食物繊維や腹筋力の不足、運動や水分の不足、過度なダイエットなどが原因として挙げられます。便が腸内に長時間留まることで硬くなり、排泄が困難になります。
器質性便秘
大腸などの消化管に何らかの疾患があり、その結果便の排泄が滞って起こる便秘です。大腸がん、腸菅の癒着や、腸閉塞などによって便の通り道が狭くなって起こる便秘です。
便秘の検査
 便秘の検査では、まず患者の腹部症状、便通状態、持病や既往歴を詳細に聴取します。その後、腹部のレントゲン検査、聴診、触診を行い、身体の状態を総合的に評価します。必要に応じて、大腸カメラ検査や血液検査を追加で実施します。特に大腸カメラ検査は、大腸粘膜を直接肉眼で観察できるため、潰瘍、炎症、狭窄などの病変を発見するのに非常に有効です。さらに、疑わしい病変が見つかった場合は、組織を採取し、病理組織検査によってより詳細な分析を行うことも可能です。
便秘の検査では、まず患者の腹部症状、便通状態、持病や既往歴を詳細に聴取します。その後、腹部のレントゲン検査、聴診、触診を行い、身体の状態を総合的に評価します。必要に応じて、大腸カメラ検査や血液検査を追加で実施します。特に大腸カメラ検査は、大腸粘膜を直接肉眼で観察できるため、潰瘍、炎症、狭窄などの病変を発見するのに非常に有効です。さらに、疑わしい病変が見つかった場合は、組織を採取し、病理組織検査によってより詳細な分析を行うことも可能です。
下痢と便秘を繰り返している
場合も当クリニックまでご相談ください
繰り返す下痢や便秘に悩まされた経験は、多くの方がお持ちのことでしょう。当クリニックには下痢や便秘でお困りの方がたくさん来院されます。原因としては、腸の状態が影響していることが考えられます。一時的なものであれば自然に改善することもありますが、長期間続く場合は病気やアレルギーが関係していることもあります。急に症状が現れた場合は、体のサインかもしれませんので、早めに専門医にご相談ください。